 |
植物成長の季節 |
|
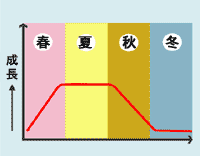
[季節と成長]
|
春:成長開始、夏:成長盛ん、秋:成長低下、冬:休止。四季に応じた植物の成長のリズムは誰でも知っています。それをもう少し詳しく知りたい、そんな調査例が、樹木の幹の微細な太りを教えてくれるデンドロメーターです。また葉の中の葉緑素の充実度を測るSPADメーター調査もあります。これらは、樹種ごとの成長の季節パターンを教えてくれます。

[デンドロメーター]
↑幹が成長した分だけベルトが広がります。 |

[SPADメーター]
↑葉をSPADメーターに挟むと、葉緑素の充実度が表示されます。 |
|
 |
物質の動き |
|
太陽からのエネルギーを受け止めて光合成した物を、人間はじめあらゆる生き物に提供してくれるのは植物。植物が環境から原料をもらって光合成し、それが植物の成長、動物の成長に利用され、落ち葉や枯死物、排泄物や死体などの生命を失った生物体を、微生物が腐らせて元の光合成の原料に戻して環境へ、この動きを物質循環といいますが、森林という緑の工場では、この過程が実にうまく作動しています。エコモニタリングはその実体を教えてくれます。
|
 |
緑の森の生産量 |
|
ある期間内の光合成による生産物(有機物)の総量のことを総生産量と言います。しかし、樹木も呼吸をしますから、呼吸で使われる量を差し引いた残りが実際に植物の体となるわけです。それを純生産量といいます。
しかし、枯れ落ちるもの(枯死量)があり、動物に食べられる分(被食量)もありますから、それらを差し引いたものが実際の植物体の増加、すなわち、
純生産量 - 枯死脱落量 - 被食量 = 植物体増加量
∴ 純生産量 = 植物体増加量 + 枯死量 + 被食量
|
ということになります。
フォレスタヒルズでは、エコモニタリングとして毎年木の太さや高さを測定しています。そのデータで毎年の森林の植物重量(絶乾重)が計算できますから、2度の調査があれは、その間の植物体増加量が求められます。一方、その間の枯死脱落量も実際に測定されています(リタートラップ)。被食量は、森林の場合は僅かで、ふつう純生産量の数%程度ですが、枯死量調査の時に虫フンなどを分けて計ってっておくと推定がききます。
とすれば、森林の純生産量が概算できるわけです。一例を挙げましょう。
未整備林の例(最近6年間を1年あたりに換算、トン/ha/年)
純生産量15.5 - 枯死量6.6 - 被食量0.8 = 植物体増加量8.1
|
|
 |
二酸化炭素吸収・固定 |
|
こうした物質の収支の数字は、森林が大気中の二酸化炭素を吸収するという最近の話題に対応できます。森林がいくら沢山二酸化炭素を吸収したとしても、それが植物体として溜め込まれないと意味がありません。したがって、肝心なのは植物体増加量なのです。
先の未整備林の例で計算してみますと、純生産量15.5トン/ha/年は6.9トン/ha/年の炭素量に換算できるので、それだけの炭素を吸収したことになりますが、この中には腐ってすぐに炭素放出に回る枯死量相当分を含みます。実質重要な炭素固定量に当たるのは植物体増加量8.1トン/ha/年で、これは炭素量に直すと3.6トン/ha/年ということになります。
なお、この炭素量は二酸化炭素にして13.2トン/ha/年。これは、人間36人分の呼吸放出量に当たる計算になります。
ついでながら、原生林のような成熟した森林では、毎年純生産量に近い量が枯死脱落し、植物体増加量はゼロに近づきますので、炭素固定に働くのは植物体増加量の大きい未成熟の若い林、ということになります。
|
![]()