 遷移とは、ある場所の植物の姿が自然に移り変わっていくことです。なにか植物があると、枯れ葉などが落ちて土がだんだん良くなり、また風をさえぎり、地面の乾燥を防ぐなど、その場所の環境条件を少しずつ改良して行きます。こうして生まれる新しい環境が次のより発達した植物の生育を許します。その繰り返しが遷移なのです。遷移が始まる場所は、乾燥地、湿潤地、砂地などいろいろありますが、それぞれの環境に強い植物がまず最初に生育して、遷移が進みだします。
遷移とは、ある場所の植物の姿が自然に移り変わっていくことです。なにか植物があると、枯れ葉などが落ちて土がだんだん良くなり、また風をさえぎり、地面の乾燥を防ぐなど、その場所の環境条件を少しずつ改良して行きます。こうして生まれる新しい環境が次のより発達した植物の生育を許します。その繰り返しが遷移なのです。遷移が始まる場所は、乾燥地、湿潤地、砂地などいろいろありますが、それぞれの環境に強い植物がまず最初に生育して、遷移が進みだします。遷移の進行、つまり植物の連続的な交代にはある一定の順序があり、このことを遷移系列といいます。例えば、陸上の乾燥した裸地から出発する遷移は、裸地→地衣・コケ→一年生草草原→多年生草草原→陽性低木林→陽性高木林→陰性高木林、というパターンで進行します。遷移が進んでその場所で最終的に到達する植物の群落、つまり遷移の終着の姿が極相です。極相に至ると群落は安定し、その状態が続きます。
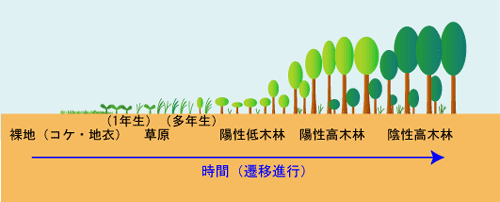
人間たちは、遷移の段階をうまくコントロールして生活してきました。例えば、遷移を途中の段階で止めて、一年生草を収穫するのが田畑ですし、多年生を利用するのが牧場です。高木収穫が林業です。
また植物達にも、それぞれ好みの遷移段階がありますから、その植物を大事にしたいなら、その段階をみとめて、そこで遷移進行が止まるような処置が必要なのです。
 「針」とは針葉樹のこと、そして「広」とは広葉樹のこと。したがって、針広混交林とは、針葉樹と広葉樹が混ざり合った森林が針広混交林です。
「針」とは針葉樹のこと、そして「広」とは広葉樹のこと。したがって、針広混交林とは、針葉樹と広葉樹が混ざり合った森林が針広混交林です。性質の違う樹種を組み合わせることによって、お互いの欠点を補いあう健全な森林を育成することが出来ます。例えば、樹形の尖った針葉樹と丸い広葉樹を組み合わせて光を効率よく使う、また風景としても優れた森林の形にする、木材量が多く保て、やせ地にも比較的強い針葉樹と、土の保全に優れた広葉樹の混交でより健全な森林とする、病虫害にも多様に対応できる(一つの原因で全滅しない)、等です。
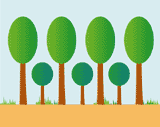
 枝葉の層が一つだけのものが単層林、二層以上を持つものが複層林。暖かいところの天然林のほとんどは、自然に複層林になっています。複層林では、上下に葉が着いていますから、その森林が受ける太陽光を無駄なく使える利点があります。人工的に複層林を作る時、上下の層に同じ樹種を使う場合もありますが、下層には上層のものよりも日陰に強い種類を使うのが普通です(例えば、上マツ類-下スギやヒノキ)。人工複層林は、一頃の皆伐作業の反省から生まれました。上層木を伐採しても、その時には下層木が生育していて裸地にならないので、土の保全等にも問題は少ない、というのがその理由でした。
枝葉の層が一つだけのものが単層林、二層以上を持つものが複層林。暖かいところの天然林のほとんどは、自然に複層林になっています。複層林では、上下に葉が着いていますから、その森林が受ける太陽光を無駄なく使える利点があります。人工的に複層林を作る時、上下の層に同じ樹種を使う場合もありますが、下層には上層のものよりも日陰に強い種類を使うのが普通です(例えば、上マツ類-下スギやヒノキ)。人工複層林は、一頃の皆伐作業の反省から生まれました。上層木を伐採しても、その時には下層木が生育していて裸地にならないので、土の保全等にも問題は少ない、というのがその理由でした。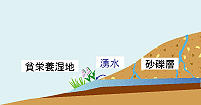
 東海地方の丘陵地には、砂礫層という養分が少なく、水を通しやすい性質の地層が分布しています。砂礫層に地下水を通しにくい粘土層が挟まっていると、地層の断面が露出する場所から地下水が湧き出し、湿地ができます。養分の少ない砂礫層を通ってきた湧水には養分はあまり含まれていません。したがって、養分の少ない(貧栄養といいます)湿地となります。
東海地方の丘陵地には、砂礫層という養分が少なく、水を通しやすい性質の地層が分布しています。砂礫層に地下水を通しにくい粘土層が挟まっていると、地層の断面が露出する場所から地下水が湧き出し、湿地ができます。養分の少ない砂礫層を通ってきた湧水には養分はあまり含まれていません。したがって、養分の少ない(貧栄養といいます)湿地となります。“湿地”と聞くと、尾瀬や釧路湿原に代表される、広大な湿原をイメージする人も多いかもしれませんが、このようにしてできた湿地の多くはとても小規模で、その大きさはせいぜい10m×10mから20m×20m程度です。
湧水による湿地は、一つ一つの湿地の寿命は長くはなく、かつては消滅と再生を繰り返していました。しかし、近年は開発などによってその数が減っています。また、新たに湿地となりうる場所も、同時に減少しています。新しい湿地の誕生が期待できない現状では、今ある湿地の保全が課題となります。
 東海地方の貧栄養湿地には、世界中でこの地域にしか生育していない植物や、分布の大半がこの地域に集中している植物がたくさんあります。これらの植物は、伊勢湾を取り囲むように分布していることから、周伊勢湾要素植物とよばれています。
東海地方の貧栄養湿地には、世界中でこの地域にしか生育していない植物や、分布の大半がこの地域に集中している植物がたくさんあります。これらの植物は、伊勢湾を取り囲むように分布していることから、周伊勢湾要素植物とよばれています。もともと分布範囲が限られているうえに、湿地自体が次々と消滅しているため、いずれも貴重な植物ばかりです。周伊勢湾地域にしか生育していない植物の主なものとしては、シデコブシやシラタマホシクサなどがあげられ、いずれも環境庁レッドデータブックの絶滅危惧種とされています。
| 種名 | フォレスタヒルズでの 生育状況 |
|---|---|
| シデコブシ | ○ |
| マメナシ | × |
| ヘビノボラズ | ○ |
| モンゴリナラ | × |
| ヒトツバタゴ | × |
| クロミノニシゴリ | ○ |
| ナガボナツハゼ | × |
| ハナノキ | × |
| ナガバノイシモチソウ | × |
| トウカイコモウセンゴケ | ○ |
| ヒメミミカキグサ | × |
| ミカワシオガマ | × |
| ミカワバイケイソウ | × |
| シラタマホシクサ | ○ |
| ウンヌケ | ○ |
 絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめた本で、国際自然保護連合(IUCN)が、1966年に初めて発行しました。IUCNから発行された初期の レッドデータブックはルーズリーフ形式のもので、もっとも危機的なランクに選ばれた生物の解説は、赤い用紙に印刷されていたことからこう呼ばれています。
絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめた本で、国際自然保護連合(IUCN)が、1966年に初めて発行しました。IUCNから発行された初期の レッドデータブックはルーズリーフ形式のもので、もっとも危機的なランクに選ばれた生物の解説は、赤い用紙に印刷されていたことからこう呼ばれています。日本でも、1991年に「日本の絶滅のおそれのある野生生物」というタイトルで環境庁(現在の環境省)がレッドデータブックを作成し、2000年からはその 改訂版が順次発行されています。愛知県では、「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物」として、植物編が2001年に、動物編が2002年に発行されています。各生物種の絶滅のおそれの程度は、次のように区分されています。
| 絶滅 | 既に絶滅したと考えられる種。 |
| 野生絶滅 | 野生では絶滅し、飼育・栽培下でのみ存続している種。 |
| 絶滅危惧IA類 | 絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 |
| 絶滅危惧IB類 | 絶滅の危機に瀕している種。IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 |
| 絶滅危惧II類 | 絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。 |
| 準絶滅危惧種 | 存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。 |