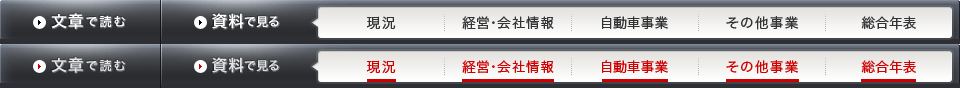TQM(Total Quality Management)
詳細解説
2. TQCの導入とデミング賞への挑戦
(1)TQCの導入(1961年)
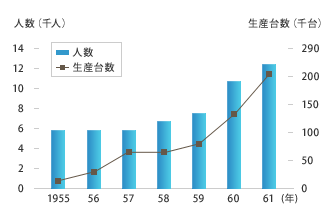
当時の生産台数・人員の増加
トヨタは、1955年(昭和30年)に本格的な乗用車である「トヨペットクラウン」を発売し、1957年にはマイカー時代に対応した小型車の「トヨペットコロナ」を発表するなど、飛躍的に生産台数を伸ばしていった。それに対応して、人員は2倍に、生産も7倍になった。
しかし、新人の増加と教育の不徹底、管理者の力不足と未熟練などの課題が散見されるようになり、品質の向上が追いついていかなかった。
こうした課題は、1960年に発表した新型「トヨペットコロナ」において、新機構サスペンションの不具合や雨漏りなどの品質問題となって表面化>した。
そこで、トヨタは、「経営管理の画期的刷新」と「良質廉価な製品の生産と開発」を図るため、従来から行われてきた品質管理を強化し、1961年にTQC(Total Quality Control)を導入した。
(2)導入期(1961年~1962年)
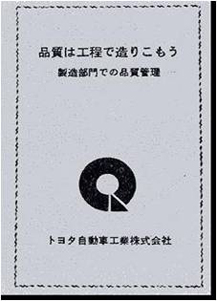
第3回品質月間パンフレット
TQCの導入期には、豊田英二副社長(当時)から「検査の理念は検査しないことにあり」という品質に関する明確な指針が示されるとともに、それまで一部だけが対象であったQC教育が全社的に展開されたり、不良半減運動が展開されるなどし、品質管理の考え方及び効用についての認識が深まっていった。これにより、現場に従来残っていた「検査を厳しくすれば品質がよくなる」という考え方が「品質は検査の前でつくる」という考え方に変化していった。
1962年(昭和37年)の「第3回品質月間」では、「品質は工程で造りこもう」と題されたパンフレットが全従業員に配布された。ここに、「品質は工程で造りこむ(自工程完結)」という言葉が誕生した。
(3)機能別管理・方針管理の導入(1963年~1964年)
TQCの推進期には、事務部門や技術部門の活動の遅れと、部門間の連携が十分でなかった点を反省し、部門間の機能的な連携が図られるよう、「品質保証」と「原価管理」を2本の柱として、これに全社的な関連をもつ「人事管理」と「事務管理」を加えた4機能を中心とした「機能別管理」の体制を整備した。
さらに、品質目標の全社的な浸透と徹底が十分ではなかったことを踏まえ、従来、その都度明らかにしていた会社の経営方針を、「基本方針」「長期方針」および「年度方針」の3部からなる「会社方針」として明文化するとともに、「会社方針」を各部門に展開し、フォローする仕組みとして「方針管理」を整備した。
これらの「機能別管理」や「方針管理」は、現在でもトヨタのマネジメントの重要な仕組みとなっている。
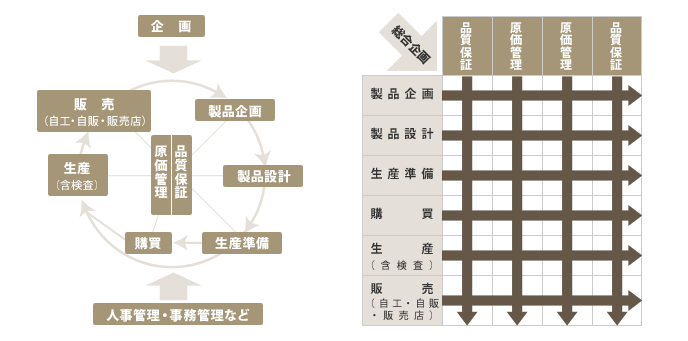
機能概念図(当時)
(4)定着期(1964年~1965年)
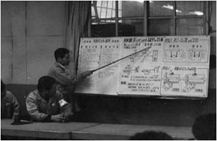
QCサークル活動の風景
TQCの定着期には、機能別管理の柱のひとつである「品質保証」について、各工程が後工程に品質を保証していくことにより最終的にお客様に品質を保証するという考え方を浸透させ、具体的な活動として定着させるため、製品企画から販売・サービスまでの各ステップを細分化し、それぞれのステップにおいて、次のステップに保証するべきこと、また、保証するためにやるべきことが「品質保証活動一覧」(現 「品質保証規則」)にまとめられた。あわせて「品質保証」とは、「消費者にとって、製品が満足であり、信頼でき、経済的であることを保証すること」と定義された。
「原価管理」についても、同様に各ステップごとの活動が整理され(現 「原価管理規則」)、管理の仕組みの標準化が進められた。
また、QC活動も全ての職層で推進組織が整備され、スタッフが取り組む「QCチーム」(1963年(昭和38年))、現場の第一線の作業者が参加する「QCサークル」(1964年)など、全員参加のTQCが展開されていった。
(5)活動の効果 デミング賞実施賞(1965年)と日本品質管理賞(1970年)
トップから現場の第一線の作業者に至るまで一丸となったTQCの推進が評価され、トヨタは、1965年(昭和40年)にデミング賞実施賞(デミング賞とは、戦後日本において品質管理の普及と品質向上の大きな礎となった故William Edwards Deming 博士の業績を記念して1951年に日本科学技術連盟が創設した賞であり、実施賞とは、優れたTQCが実施されている企業や組織に授与されるもの)を受賞した。
-

デミングメダル
-

デミング博士から祝福される中川不器男社長(当時)
その後も、1966年度の会社方針では、「オールトヨタで品質保証」をスローガンに、社内の総合管理体制をさらに充実し、発展させることに重点が置かれた。また、トヨタとグループ会社の間で8社QC連絡会を設置し、仕入先から販売会社を含めた「オールトヨタで品質保証」を行うための具体策について、検討および情報交換を行うようになり、グループ各社も次々とTQCを導入することとなった。
こうしたTQCを強化するための取組みが評価され、1970年には日本品質管理賞(1969年に東京で開催された品質管理国際会議を記念して創設され、デミング賞実施賞の受賞後も3年以上継続的にTQCを実施し、その水準が向上・発展していると認められた企業や組織に授与される賞)の受賞第1号の栄誉に浴した。
TQCの導入とデミング賞への挑戦は、トヨタに多くの成果をもたらした。
有形の効果としては、TQC導入まで増加傾向だった台あたり材加不・不具合が半分以下に減少した。これを受けて新車購入後の保証も、1963年(昭和38年)3月には「1年または2万キロ」であったところを、1967年4月には「2年または5万キロ」と他社に先がけて延長し、国際水準の保証条件を確立することができた。
無形の効果としては、品質に対する社員の意識の変化があり、全員参加のTQCにより、トップから現場の第一線で働くメンバーまで一人ひとりが品質保証の主役として、改善を実施することができた。
その意義を、「経営の視点」と「一人ひとりの働き方の視点」からまとめると、前者は機能別管理や方針管理など現在に至るマネジメントの基本的な仕組みが整備されたことであり、後者は自工程完結やPDCAなど「QC的ものの見方・考え方」が浸透し、仕事の基本が形成されたことである。

豊田章一郎常務取締役(当時)
「会社の体質が非常に改善された」
「ひとつの目標に向かって協力してゆく体制が、TQCという手法を通じてでき上がった」
QC推進本部副本部長
豊田章一郎 常務取締役(当時)の講演より