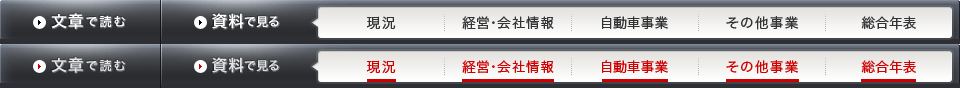実車4輪多軸台上耐久試験機、およびその6軸化
悪路走行耐久試験を台上化することで、実車では3カ月程度かかるところ、試験機の昼夜連続運転により2~3週間で評価が可能となり、精度向上とともに画期的な効率化を実現した。
導入にあたっては、数社のシステムを総合的に検討し、当時の品質保証部計量課とも議論を重ねた。その結果、大型耐久試験装置で定評のあるMTS社の装置に決定した。
1機の導入から始まり、今では3機が稼働している。現在は、パソコンなど周辺装置の進歩によってほとんどのプロセスがデジタル化され、制御装置も小型化している。本体装置も6軸制御に進化、また応用として貨車輸送を再現する試験法も開発した。
-

多軸台上耐久試験機
-

多軸台上耐久機で貨車輸送の耐久試験
第1車両技術部新設、第1車両技術部大改編
FP組織改正(センター制)の仕上げとして研究開発組織の再編・強化が行われ、3室1課から成る第1車両技術部が先行開発を使命に新設された。第1開発室は主に設計技術者が、第2開発室には実験技術者が集まった。大多数は、旧東富士第11開発部の移管メンバーで、本社の実験部からは技術室の数名が異動した。
発足から2年後、第1車両技術部が1~7Kのグループに大幅改編された。各グループの機能主査は、性能毎の総責任者であり、世界一流のエンジニアでもある。役割が次のように定義されている。
- ・先行開発シナリオの立案と推進
- ・製品開発との関わり実験部の目標性能と性能予測に対する監査、車両レベルの確認
- ・性能別連絡会の主催・推進
- ・先行開発体制の整備、情報収集・予算・設備・研究委託・人材育成の充実
先行開発担当の第1実験部技術室は、この時解散し、第1車両技術部へ移管された。他にも多数のベテランが第1~3実験部から第1車両技術部へ異動した。
1K…ボデー開発、2K…安全、3K…熱・流体、4K…信頼性・強度、5K…車両運動、6K…NV・乗心地、7K…人間工学
衝突安全ボデー GOA
GOA(Global Outstanding Assessment)とは、クラス世界トップレベルの安全性能を追求するために設定したトヨタ独自の目標性能のことであるが、「安全」が商品力の一つとして捉えられるきっかけとなったと考えられる。時を同じくして、1995年にJNCAPと呼ばれる衝突性能アセスメントが導入され自動車業界全体を巻き込んだ安全技術開発競争に拍車がかかり、急速に自動車の衝突安全性能が向上した。
「GOA下さい」で始まる1996年からのトヨタの安全訴求キャンペーンは、それまであまり目にすることのなかった衝突実験映像が話題となった。
車両CAE部
1999年からヴァーチャルエンジニアリング技術の進化に伴い、新しい車両開発手法である「BR-AD」プロセスが構築され、構造計画段階から高い設計完成度を持った図面の創出が要求されるようになった。翌年にはボデー設計、シャシー設計、実験部署を中心にCAE(Computer Aided Engineering)やナレッジを活用した設計、性能予測技術のニーズが高まり、各機能の性能を世界トップレベルに高め、突出したパフォーマンスを確保する車両開発手法への具体化が始まった。これを契機に2003年1月に実験部の各機能のCAE組織を統合して第1車両技術部内に集約、さらに7月にはボデー設計、シャシー設計、実験部のCAE組織を統合し「車両CAE部」を創設した。これ以降、車両開発プロセスはCAEの活用を前提したプロセスに移行し、CAEによる図面段階での性能予測や品質向上は、車両開発を効率化する上で不可欠な工程となった。
車両性能開発部発足
特にセンター制以降、車両性能・品質開発の責任部署として、実験部の役割が出図前および号試以降で拡大した。2005年1月、その幅広い使命・機能をより判り易く表現し、部内外の意思を統一して車両開発体制の整備・充実に役立てるため、部・室名称を「レクサス車両性能開発部」 「第1車両性能開発部」「第2車両性能開発部」「士別車両性能開発部」と見直した。
同時に、部長のプロジェクト指導・推進をより明確にするため、第2レクサス実験室・第1商品実験室・第2商品実験室内の開発推進要員を部付に集め、「プロジェクト開発推進G」「性能確認G」「お客様評価G」と名付け、部長直轄とした。
GI20性能別組織に再編
1992年9月以来、約16年続いた車種別センター制は、車種軸から見ると期間短縮・プロジェクト数増加に対応する手段として、有効であった。反面、性能軸から見ると、専門グループがセンターや部署を越え、細分化された弊害が蓄積された。特に多種の専門性能から構成される実験領域では、新人育成の遅れ、一部、技術員への負荷集中、研究・先行開発へのベテランシフトが困難、などが課題となってきていた。2008年6月のGI20組織改正で、実験領域は、性能別組織を再評価して大幅に取り入れた。ただし、一部専門で車種軸の考えを残し、効率的で見通しの良い組織編成とし、「車両実験統括部」 「第1車両実験部」「第2車両実験部」「車両技術開発部」「士別車両実験部」「車両統合技術開発室」の5部1室とした。
組織再編に際して考慮した実験3部の課題と対応は、次のとおりである。
- ・ 専門知見の集約・横展: 専門性能を同一の部へ集中
- ・ 専門性能の人材育成: 専門性能を同一の部へ集中
- ・ 負荷変動への柔軟な対応: 専門性能を同一の部へ集中
- ・ 新プラットフォームの一気通貫開発*: プラットフォーム実験室新設
- *
- 同じ技術員が「先行から量産まで」を担当すること:引継ぎを廃止し、開発を効率化
- ・ 領域マネジメント強化: 車両実験統括部を新設
このとき、技術領域(エンジン・駆動・シャシー・ボデー・実験)の枠を越えた先行技術開発のため、車両統合技術開発室が新設された。旧第1車両技術部は車両技術開発部へ名称変更。第1車両技術部設立当初からの1K(ボデー開発G)は、ボデー設計領域へ戻った。旧第1車両性能開発部第1信頼性開発室の防錆Gは、技術領域を越え、車両材料技術部塗装設計室へ移管された。