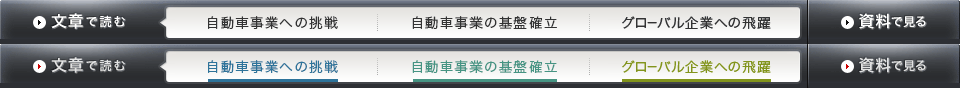第1節 リコール問題への対応
第1項 リコール問題の発生
1960年代から1970年代にかけて、日本は高度経済成長を遂げ、1968(昭和43)年に米国に次ぐ世界第2位のGNP(国民総生産)大国へと発展していった。国民生活の向上も目覚ましく、「豊かな社会」が実現する。1960年代後半からは、かつての「三種の神器」(白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機)に代わって、カー、カラーテレビ、クーラーの「3C」が急速に普及していった。その一方で、消費者物価が上昇し、公害問題、都市問題なども発生し、それまでの成長を優先する考え方が徐々に見直されるようになった。
また、モータリゼーションの進展に伴って、自動車が広く人々の生活のなかに浸透していった反面、交通事故の増大、都市の交通渋滞、生活環境の悪化なども表面化し、自動車に対する見直しが行われるようになった。
米国においても交通事故の増加が問題になっていた。1966年、弁護士ラルフ・ネーダーは、その著書『Unsafe at Any Speed』1で、GMのコルベアが転覆した事故を取り上げ、交通事故が運転者の法規違反や不注意によるという考え方を批判し、自動車の安全設計こそが交通事故を防ぐと強く主張した。特に、自動車が衝突した際、乗員がそのショックで車内のどこかに衝突する2次衝突が危険であるとし、その対策の必要性を強調した。
この図書をきっかけに米国では自動車に対する安全を要求する世論が盛り上がり、1966年9月に「国家交通・自動車安全法2」により、リコール制度が制定された。こうして、自動車メーカーが自動車の構造上の欠陥を発見した場合、商務省の交通安全局3に届け出て、ユーザーに通知するとともに回収修理などを行うことになった。
一方、日本では米国と異なり、6カ月ごとの法定定期点検や2年ごと(トラックでは1年ごと)の車検制度があり、市場に出回っている車は車両検査を受けていた。このため、市場に出ている車に大きな不具合があるとは考えられていなかったこともあり、自動車メーカーが不具合に気づいた時に、ユーザーに直接通知し修理するのが慣例になっていた。
1969年6月1日、『朝日新聞』は朝刊社会面のトップ記事で、「日本の自動車 欠陥なぜ隠す 日産・トヨタを米紙が批判」と報道した。『ニューヨーク・タイムズ』が、「アメリカで日本およびヨーロッパの自動車がリコール問題を起しても、メーカーはそれを公表せず、独自の方法で欠陥車を回収・修理している」と批判した記事を受けたもので、具体的な事例としてトヨタ・コロナのブレーキ故障と日産・ブルーバードのガソリン漏れを掲げた。4この記事は国内で大きな反響を呼び、自動車業界は厳しい世論の追及を受け、リコール問題に発展した。
事態を重視した運輸省は、トヨタ、日産の両社から実情を聴取するとともに、自動車業界各社に対して通達を出し、市場に出ている各社の車の総点検を指示した。自動車業界は、同月(6月)9日の日本自動車工業会常任委員会で「使用者に対する周知徹底の方法については、従来の方法に加えて、必要に応じて報道機関を通じて徹底をはかる」ことを申し合わせた。5同月11日、業界各社は運輸省に対策車の詳細とその回収対策を届け出るとともに、翌12日には、それぞれリコール車の新聞広告を実施した。一方、届出を受けた運輸省は同月16日、日本自動車工業会加盟12社の対策車リストを公表した。
運輸省ではリコール制度を確立するため、同年(1969年)8月に「自動車型式指定規則」を改正して、「設計又は生産過程に起因する欠陥に対する措置」を定め、リコール車の公表を義務づけた。
リコール問題は、これまで順調に伸びてきた自動車業界に課された一つの大きな試練であった。消費者運動も高まりを見せ、業界各社は自動車の安全と品質問題の重要性を改めて認識するとともに、自動車産業が単に経済的側面のみならず、広く社会生活にも大きな影響をもつ存在になっていることを再確認した。