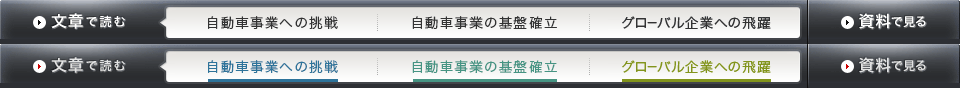第3節 基礎技術の研究・開発
第1項 研究所の設立
豊田喜一郎は、自助努力による独自の技術開発が工業の発達を促し、そのためには絶えざる研究と創造が必要であると考えていた。例えば、次のような言葉が残されている。
喜一郎は、実際技術(実技)とともに学術的研究を重視し、1936(昭和11)年5月に東京芝浦に研究所を開設した。同年4月に豊田自動織機製作所自動車部へ入社した豊田英二が、それを担当した。喜一郎の学術的研究に対する考え方がうかがえる言葉として、以下のような発言がある。
(自動車工業は)最新学術の応用が伴う最も文明の先端を行く可き工業であります。一技術者の智識に非ずして各方面の智識力の集合に依って成り立つ工業で有ります。2
喜一郎によれば、技術は実際技術と学術的研究が密接にかかわりあって進歩していくものであった。現場の側からは、「試作品をつくるときは、まず現場のものを呼んでつくらせ、その調子がよいと、それから学校出に理論づけをさせられた」と証言している。3
芝浦の研究所では、ラジエーター、木炭車のガス発生器、国産自動車部品などの調査や、ドイツ車DKWの分解・スケッチなどのほか、工作機械、フランス製軽飛行機「プウ」やヘリコプター、オートジャイロ、ロケットなど航空関係の調査が行われた。
豊田自動織機製作所自動車部の研究所は、トヨタ自動車工業の設立に伴い、1937年8月にトヨタ自動車工業の研究部となった。研究顧問には、喜一郎の友人である学者たちが就任した。4
研究テーマとしては、歯車、ラジエーター、クランクシャフト、プレス加工、鉄板などの各種材料、エンジンの性能などがあり、高校・大学時代の友人たちが調査・研究を支援した。それらの調査・研究の成果を雑誌『機械及電気』(1936年5月創刊)に掲載し、最新知識の吸収と普及に努めながら研究開発を進めた。同誌には研究顧問に就任した研究者を中心に、多数の論文が掲載された。5