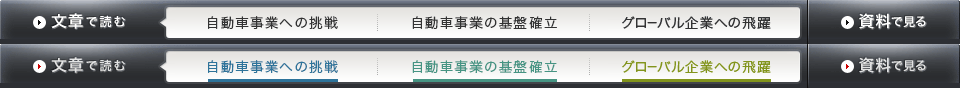第8節 本格的乗用車トヨペット・クラウンの登場
第3項 本格的乗用車トヨペット・クラウンの開発
国産技術による独自の開発
1950(昭和25)年ごろになると、経済復興の進展に伴って、タクシー用乗用車の需要が増大し、外国製乗用車の輸入自由化に対する要望が強まった。国内自動車メーカーの乗用車の生産制限は、GHQ(連合国軍総司令部)によって1949年10月に解除されたばかりであったが、こうした動きに対応して、本格的な乗用車の開発を急ぐ必要があった。
トヨタ自工では、トヨペット乗用車として、SA型、SD型、SF型系、SH・RH型系を販売してきたが、それらはトヨタ自工製のシャシーに、ボデー・メーカーが設計・製造したボデーを架装したものであった。トヨペットの名を冠しているものの、このような販売形態をとっている限り、本格的な乗用車を提供することは難しかった。そこでまず、自社で製造した製品に対して、販売価格と品質保証に責任をもてる体制の確立に取り組んだ。
1952年7月26日、トヨタ自工の石田退三社長は、第13回国会第36回参議院運輸委員会に、業界関係者5人とともに参考人の1人として出席した。その際、国産乗用車の小売価格は販売店が自由に設定し、トヨタ自工は責任をもって定価提示ができない状況であったと述べている。1これを是正するため、トヨタ自工では、1951年8月発売のBX型トラックから、自社設計による全鋼製完成キャブ付きシャシーで出荷していた(キャブはトヨタ車体製)。完成車として出荷することにより、トヨタ自工が定価の設定や品質保証の責任を担う体制を目指したのである。
また、石田社長は参議院運輸委員会での質問に答えて、「私どもの技術が追いつかんようなことなら、私も今日のお叱りに従って、あえて国産車をやめるというくらいの気構えは持っておるのであります」、「必ず近い将来において、或る程度よくやったと言われるような時代が来ると思って私どもは実は楽しみにいたしております」と述べている。トヨタ自工は、国産技術によって乗用車を開発する方針であり、それを近い将来実現してみせるとの決意を控えめに表明した発言であった。
当時、国内の自動車業界では、乗用車の生産に関して外国メーカーとの技術提携が相次いで行われた。三菱重工業が米国のカイザー・フレーザー社と提携し、1951年6月から乗用車「ヘンリーJ」の組立生産を開始したのを皮切りに、1952年7月に日野ヂーゼル工業(現・日野自動車)がフランスのルノー公団と乗用車「ルノー4CV」の製造・販売に関する提携を、同年12月に日産自動車がイギリスのオースチン社と乗用車「オースチンA40」に関する技術提携を、1953年2月にはいすゞ自動車がイギリスのルーツ社と乗用車「ヒルマン・ミンクス」に関する技術提携を結んだ。
このような状況のなかで、トヨタ自工は純国産技術による開発を表明したのである。ジャーナリズムの評価は、トヨタ自工を時流に乗り遅れた田舎会社とする向きがあった半面、外国技術の導入に走る企業への批判的な見方も存在するなど、国産乗用車の行方が各方面の関心を集めた。
トヨタ自工にとって、豊田佐吉、喜一郎以来の自助努力による研究と創造の信念から、乗用車を自主開発するのは当然のことであった。この年(1952年)の3月に急逝した喜一郎の指示に基づき、トヨタ自工ではすでに1月から本格的な乗用車の開発を開始していた。
さらに、石田社長の発言で注目されるのは、「一つのボデーのプレス化によって相当額引下げもできるであろうということを期待しております」と述べている点である。新型乗用車の第2次試作モデルが完成していた1952年7月の時点では、ボデーをプレス成形パネルで構成する方針が固まっており、それによる製造原価の引き下げが期待できるとの趣旨であった。ただし、トヨタ自工では、車両本体の開発より前に、エンジンの開発が進んでいた。