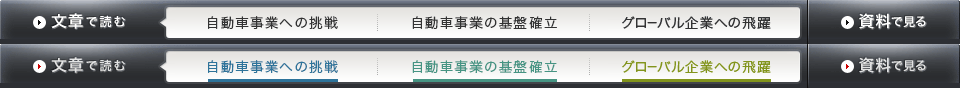第1節 バブル崩壊後の日本経済・国内市場
第1項 バブル崩壊後の国内経済
長期不況と円高の進展
バブル経済の崩壊は、1991(平成3)年から始まり、その後の日本経済は長期にわたり低迷状態に陥った。バブル崩壊の引き金となったのは、1990年末に大蔵省(現・財務省)が金融機関に通達した土地関連融資の「総量規制」と、不動産・建設業・ノンバンク向け融資の実態報告を求める「3業種規制」であった。
すでに首都圏を中心に下落が始まっていた地価は、1991年末ごろから全国に波及していった。1989年末に3万8,915円の史上最高値をつけた日経平均株価も、1990年10月に一時2万円台を割り込み、1992年8月には1万4,000円台に突入した。また、銀行の自己資本比率を8%以上とする国際決済銀行(BIS)規制が、1992年度末から日本の大手銀行にも適用されたため、自己資本比率低下に苦しむ金融機関は、いわゆる貸し渋り、貸し剥がしに動いた。企業倒産は過去最多のペースで推移し、それが金融機関の不良債権を増大させるという悪循環をもたらした。
企業の業績不振は著しく、債務、設備、雇用という3つの「過剰」が経営の圧迫要因として顕在化した。バブル期に抱えた余剰人員の削減が相次ぎ、本来は事業の再構築を意味する「リストラ」が人員削減を示す用語として定着していった。自動車業界でも、1993年秋には雇用調整助成金の支給を受けてレイオフ(一時帰休)の実施に踏み切る企業が現れるなど、深刻な事態に陥った。また、同年には日産自動車が1995年に神奈川県の座間工場での車両組立終了を決めるなど、余剰設備の解消に向けた動きも表面化した。
企業業績や雇用の悪化によって内需が著しく冷え込むなか、日本経済の命脈であった輸出に打撃を与える円高が1993年からじわじわと進行した。バブル崩壊後も、日本は貿易・経常収支とも黒字を続けており、投機筋を含む円買い需要が膨らんだためであった。1994年6月に初めて1ドル100円を割り込んだ円の為替相場は、翌1995年3月に80円台に突入、4月19日には東京外国為替市場で最高値となる79円75銭を記録した。事態を重く見た日本政府は、米国から協調策を引き出して市場介入し、同年10月以降は100円台に戻していった。