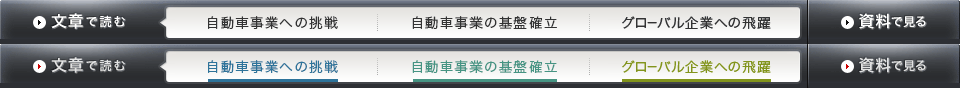第2節 豊田佐吉の事業
第1項 豊田式織機株式会社における挫折
豊田式織機株式会社の設立
1906(明治39)年1月に島崎町工場が完成し、武平町から島崎町に移転した豊田商会は、「38年式織機」の改良型である「39年式織機」、経糸停止装置を省略して機能を簡素化した低廉な「軽便織機」と、相次いで新機種を発売した。軽便織機は能率が良いうえに、価格が半額程度であったところから好評を博し、39年式織機をしのぐ売れ行きとなった。
38年式織機をはじめ、豊田佐吉がこれまでに発明した織機は、小幅織機1と呼ばれる動力織機である。それぞれの織幅は、軽便織機が鯨尺21尺2寸(45.5㎝)、38年式織機と39年式織機が鯨尺1尺3寸(49.2㎝)であった。小幅織機で生産された織物は、日本国内、朝鮮半島、中国などの市場に出荷された。
島崎町工場の織布試験工場では、小幅動力織機120台を営業用に運転した。すでに武平町工場で80台、西新町工場で100台が稼働していたので、織機の運転台数は合計300台となった。その結果、織布部門の収益も大幅に増加し、業績は好調に推移した。
評価を高めた豊田商会の小幅織機に注目したのが、三井物産大阪支店の藤野亀之助支店長であった。藤野支店長は、織機の生産能力を増強するため、1906年5月に豊田商会を株式会社に改組することを提案した。
当時、日本の綿紡績業界では、生産設備の過剰から中小紡績会社の合併・統合が進み、紡績会社数は1900年の79社から、1908年には36社へと半減していた。さらに、大日本紡績連合会の統制のもとで、操業短縮が実施される状況にあった。一方、付加価値の高い綿布に加工して輸出を促進し、過剰綿糸を削減する方策が立てられた。それを実現するには、織布を効率的に生産できる動力織機の普及が不可欠であった。3
1906年の織機の設置台数を見ると、手織機が71万6,171台、小幅力織機(小幅動力織機)が2万657台、紡績会社が兼営する織布部門の広幅織機が9,601台であった。これに対して機業家数は46万3,165戸を数え、ほとんどが手織機による零細な機織業で占められていた。4
そこで、動力織機メーカーの豊田商会に白羽の矢が立ったのである。しかし、個人事業の豊田商会は資金力に限界があり、織機の供給能力を高めるには、株式会社に改組して事業を拡大する必要があった。
佐吉は大いに迷ったが、これまで事業に協力してくれた三井物産藤野支店長からの推奨でもあったので、断るわけにもいかず、島崎町工場を現物出資して、株式会社に改組することを決めた。佐吉が所有する特許権の使用対価については、利益金から株主配当(1割)を控除した額の3分の1とされた。佐吉は、島崎町工場以外の豊田商会の事業を整理して、それまで協力してくれた弟たちや従業員たちに報い、自身は新会社へ命運を託すことになった。
こうして、1907年2月、名古屋市島崎町に資本金100万円の豊田式織機株式会社が設立された。社長には谷口房蔵が就任し、佐吉は常務取締役技師長に就任した。
なお、同社の発起人には、谷口房蔵(大阪合同紡績)、田中市太郎、志方勢七(以上、日本綿花)、山辺丈夫(大阪紡績)、藤本清兵衛(岸和田紡績)、岡谷惣助(名古屋紡績)、伊藤伝七、斎藤恒三(以上、三重紡績)などが名を連ねていた。設立の経緯から、綿紡績関係者が多いのは当然であった。