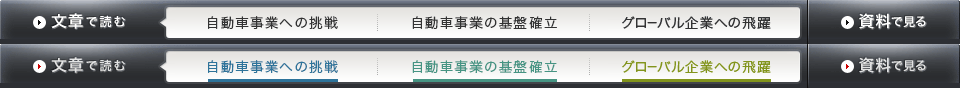第3節 基礎技術の研究・開発
第6項 ゴム部品の研究・開発
刈谷工場でのゴム部品製造
1936年5月、豊田自動織機製作所自動車部の自動車組立工場が完成したのに伴い、ブレーキ試験工場のゴム部品製造工程は、シャシー組立工場の一部となり、面積約200坪(約660m2)の区画に移転した。ゴム部品の開発に携わっていた技術者は、製鋼部研究室所属のまま移動し、新たにゴム製品の製造経験者4人が加わるとともに、ゴム部品製造設備も増強された。1
その後、油圧ブレーキ・ホースの開発に着手し、米国ワーグナー社製の油圧ホースを参考として試作にとりかかった。内管ゴムと外装ゴムには天然ゴムの最上級品を、耐圧層には長繊維のエジプト綿糸を筒状に編んで用い、一応実用に耐えうるホースの試作に成功した。こうして、ブレーキ用ゴム部品の試作が一段落したことから、押出製品、防振ゴム、ファンベルトなどのゴム部品の試作が追加され、試作から実用化へと進展していった。
1938年以降は輸入品から国産品への切り替えが進み、ブレーキ・マスター・シリンダーは日本エヤーブレーキ製が採用された。ブレーキオイルについては、同年から東京理化学工業所製のハイドローリック・ブレーキオイルが、さらに日本ブレーキオイル商会製の難揮発性ブレーキオイルが、それぞれ純正品として採用された。
1938年11月には挙母工場の完成に伴い、豊田自動織機製作所製鋼部研究室化学試験室でゴム部品の開発に携わってきた技術者は、トヨタ自工に移籍し、刈谷工場のゴム工場所属となった。1939年の職制表によれば、ゴム工場の名称は研究部刈谷出張所である。
一方、1938年には「タイヤ飢饉」が発生した。同年1月から国際収支調整のため生ゴム輸入が制限され、タイヤ出荷は逐次減少し、10月になると通常供給量の1割に激減、11月には供給停止となったのである。
このような状況から、タイヤの内製化が検討され、専門の技術者を採用して製造設備の導入を進めた。刈谷工場のゴム工場では、1940~41年に500本ほどのタイヤが試作されたという。2
しかし、戦争の影響による生ゴム需給の逼迫から、商工省の許可が得られなかったため、タイヤの試作は中止され、製造設備は天津に移設されることになった。天津でタイヤ製造設備を受け入れたのは、怡豊橡皮(いほうごむ)工廠である。同社は、横浜護謨(横浜ゴム)、出淵仲次、裕豊紗廠(東洋紡績の中国名称)、豊田紗廠(豊田紡織廠の中国名)の4者が等分に出資した資本金160万円のゴム製品製造会社である。1942年8月にトヨタ自工から移譲された設備を天津市伊太利租界15号路の工場に設置し、航空機用タイヤを製造した。3
ゴム工場では、1938年のタイヤ飢饉をきっかけに、硬質ゴム製のステアリング・ホイールの材料を酢酸セルロース樹脂に転換する研究を開始した。酢酸セルロースは、庄内川レーヨンが人絹糸を紡出する際の原料として製造していたので、きわめて有利な材料であった。研究開発の結果、熱可塑性の酢酸セルロース樹脂を用いたステアリング・ホイールの試作に成功したものの、酢酸セルロースの原料であるパルプの入手も困難となり、材料転換は試作の段階で終わった。
ゴム部品の製造が試作の域を脱し、本格的な生産を始めた1942年2月、研究部刈谷出張所は刈谷工場ゴム課と改称した。そして、刈谷工場ゴム課は、1943年5月に「企業整備令」により国華工業株式会社に統合された。製造設備は旧菊井織布工場へ移転され、国華工業名古屋工場として操業を開始した。菊井織布工場の旧称は豊田織布菊井工場で、もともと豊田佐吉の末弟の佐助が経営した工場である。織布を専業とし、紡績部門がなかったため、豊田系・東綿系の紡績工場5社の合併に加わらず、事実上の遊休工場となっていた。4