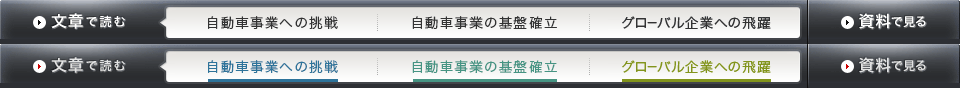第7節 グローバリゼーションを支えた各機能
第2項 原価低減と品質確保
内製原価の低減
「CCC21(Construction of Cost Competitiveness 21)」活動と並行して、2002(平成14)年度から「BT2(BREAK THROUGH TOYOTA)」活動が本格的にスタートした。BT2事務局が事前に行った競合他社とのベンチマーク調査によると、トヨタ車のコスト・品質が劣っているケースも、決して少なくないことが判明していた。
BT2活動のテーマの一つである「内製競争力の強化」では、生産技術および生産部門が経理や調達部門と協力しながら、「内製原価の見える化」など工場運営改革を進める一方、「設備のシンプル・スリム化」といった画期的な生産技術開発にも取り組んだ。
このうち内製原価については、1993年から経理部が中心になって開発していたそれまでの「工場総費用システム」をベースに、工場原価管理制度の見直しを行い、2003年4月に新たな「総費用管理システム」に深化させた。従来は変動費中心だった管理を、保全費や償却費などの固定費を含む「発生費用総額」へと範囲を拡大し、全体を把握したうえで原価改善を図るという改革だった。BT2活動の終了後も、工場の原価対策については、2006年に専門のワーキンググループを発足させ、費目別評価方法の統一による「工場改善分析システム」を構築した。
生産設備に関する改善では、一例としてシリンダーヘッドやシリンダーブロックの鋳造ラインで、設備メーカーの協力を得ながら実現した「シンプル・スリム化」がある。シリンダーブロックのダイカスト鋳造設備では、機械本体に世界初の開閉機構を採用するなど小型高精度化を図り、V6型エンジン用の場合、従来比で投資総額、設置スペースともに50%削減を実現した。2003年の初号機を皮切りにグローバル展開し、2008年時点で関連会社を含み約100ラインが導入された。
BT2活動では、生産体制や物流のスリム化をねらい、生産ラインなどの統合・集約化を意味する「寄せ停め」も推進した。車両生産で、トラック系の再編を図ったほか、エンジンなどのユニット系でも工場単位の思い切った寄せ停めを実施した。また、完成車の物流においても、中部主要港4港から出荷していたのを、原則として愛知県の名古屋港と田原港に寄せ停めすることで、費用の低減につなげた。