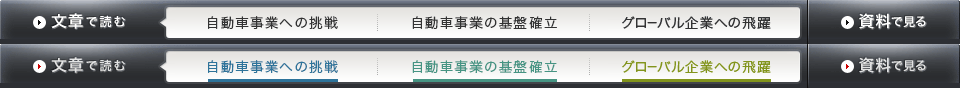第8節 本格的乗用車トヨペット・クラウンの登場
第1項 S型エンジン搭載の小型車開発
トヨペット・ライト・トラックSKB型
1953(昭和28)年9月にRH型系乗用車トヨペット・スーパーや、RK型トヨペット・トラックが登場すると、顧客の購買志向はこれら出力の大きなR型エンジン搭載車へと傾いていった。
こうした状況に対して、S型エンジン搭載車の需要増大を図るため、低廉、簡素、実用本位の軽トラックの開発が企画された。具体的には、1954年春からボンネット式SK型トラック・シャシーを基礎に、キャブオーバー式車両の設計を進めた。開発にあたっては、生産分担に従って、トヨタ自工がシャシーを、豊田自動織機製作所がエンジンを、トヨタ車体がボデーを担当し、各社の技術陣を動員した。その結果、きわめて短い期間で新型車が完成し、同年9月にトヨペット・ライト・トラックSKB型(トヨエースの前身)として発売された。
小型トラックSKB型とSK型の仕様・諸元は、表1-30のとおりである。SKB型はSK型と比べて、全長やシャシーの大きさはほとんど同じであったが、荷台内側長が2,525mmへと568mm(29%)拡張され、キャブオーバー式の特徴が発揮されていた。
表1-30 SKB型・SK型小型トラックの仕様(1955年)
|
項目
|
SKB型
|
SK型
|
|---|---|---|
|
全長
|
4,237mm
|
4,265mm
|
|
全幅
|
1,675mm
|
1,674mm
|
|
全高
|
1,850mm
|
1,735mm
|
|
ホイール・ベース
|
2,500mm
|
2,500mm
|
|
トレッド(前)
|
1,325mm
|
1,325mm
|
|
トレッド(後)
|
1,350mm
|
1,350mm
|
|
シャシー重量
|
730kg
|
815kg
|
|
車両重量
|
1,130kg
|
1,175kg
|
|
最大積載量
|
1,000kg
|
1,000kg
|
|
エンジン
|
S型(30馬力)
|
S型(28馬力)
|
- (出典)
- トヨタ技術会『技術の友』1955年3月5日
トヨペット・ライト・トラックSKB型に関して特筆すべきは、これまでの小型トラック(SB型、SG型、SK型)のように、シャシーで販売する方式を取りやめ、トラック完成車として販売したことである。トヨタ自販の業務であったボデー製作は、トヨタ自工が管理する生産工程のもとに置かれ、トヨタ車体で行われることになった。一方、完成車販売方式に組み込まれたボデー・メーカーは、トヨタ自工の分工場的な位置づけとなり、製造技術や品質管理、生産管理などの管理技術なども、トヨタ自工と同じ水準が求められた。1トヨタ自工は、この完成車販売方式により、車両の販売価格設定と品質保証に責任を持つようになったのである。
翌1955年には「設備近代化5カ年計画」による合理化の効果や、同年1月に発売された初代「トヨペット・クラウンRS型」(後述)の内製ボデー架装完成車販売による収益性向上に支えられて、トヨタ自工の利益率は高い水準で推移した。3このような好業績を背景に、SKB型トラックの大幅値下げを計画し、1955年暮にはトヨタ車体の生産設備増強を進めた。
1956年1月1日、トヨタはSKB型トラックの価格を56万円に値下げし、同クラス三輪車との価格差を12万5,000円(29%)に縮小した。これにより、折からの好景気とも相まって、SKB型トラックの需要は伸長し始めた。さらに、同年5月17日には53万8,000円へと値下げしたことで、翌6月の生産台数は1,052台に急増した。
1956年にはSKB型トラックの愛称を公募し、7月に「トヨエース」と決定した。トヨエースは、トラックの国民車として、文字どおりエースの地位を占め、トヨタ自動車の1府県複数店方式、いわゆる複数販売店制への移行を後押しする推進役を果たすとともに、三輪車業界が四輪車市場に参入する気運を生んだ。